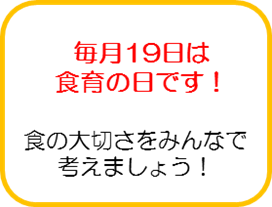本文
「共食」は低栄養を救う(令和6年度2月号)
「共食」は低栄養を救う
みなさんは「共食」という言葉をご存知でしょうか。
誰かと食事をとることを指し、社会的交流の1つにあたります。
「第4次・健康たかつき21」によると、市民の行動指針に「今より「共食」の回数を週1回以上増やします」と掲げられています。
現在、成人では8.4回で、目標である11回に達していません。
(※朝食または夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数。1週間すべて「共食」した場合は14回とする)
共食のいいところ
「自分が健康だと感じること」や「健康的で規則正しい食生活」や「望ましい生活のリズム」は共食と関連していることが、日本人を対象にした研究で明らかになっています(※1)。
たとえば高齢期の孤食(1人でとる食事)は低栄養やうつ病の危険因子である(※2)一方、共食は様々な食材を摂取し、食事の満足度や栄養状態を良くすることがわかっています(※3)(※4)。
食事中にお互いが様々な情報交換をして、新たな食への興味関心につながったという経験はないでしょうか。
このように、共食は低栄養予防の基盤ともいえます。
(※1)農林水産省ホームページ
(※2)Tani Y,et al.:Appetite 2015;95:1-8
(※3)Kimura Y,et al.:Journal of Nutrition,Health and Aging 2012;16-8:728-731
(※4)山之井 麻衣 他:日本地域看護学会誌 2013;16-2:15-22
共食をあきらめない
では、ひとり暮らしだと共食は出来ないのでしょうか?
親しい人との食事や、地域の食事会への参加など、社会的交流がおすすめです。
たとえば、おおむね65歳以上の人が5人以上集まる体操グループが約270か所あり、「ますます元気体操」「もてもて筋力アップ体操」を行うほか、食事会・茶話会などのお楽しみを設ける所もあります。
参加ご希望の際は、長寿介護課へお問い合わせ下さい。
また、趣味活動・カフェ・体操などを実施している「集いの場」もあり、ご興味に応じて利用するのも良いでしょう。
「体操拠点」についての詳細は、下記リンクからご覧ください。
自主グループ活動のご紹介
「集いの場」についての詳細は、下記リンクからご覧ください。
高齢者集いの場ガイド ちょっと寄りたい街の縁側
高齢期の体の衰え「フレイル」は、外出等の機会が少なくなることから始まるといわれています。
地域とつながり気持ちをワクワクさせながら、美味しく栄養をとれるといいですね。
記事作成:長寿介護課(072-674-7166)